なぜ、FXでは「政策金利」が通貨の価値を左右していくのでしょうか。「政策金利」がわずか0.25%変わっただけでも、相場の流れに多大な影響を与えます。
「利上げ」「利下げ」「金利」とかって・・・
いったい何なの?
「政策金利」と聞くと、なんだか難しそうです。しかし、「預金」や「ローン」という観点で「政策金利」を見ていけば、「政策金利」と「FX」の関係は簡単に理解できます。
今回は、どこよりもわかりやすく、かつ楽しみながら「FX」と「金利」の関係を解説していきます。どうぞ、お気軽に最後までお付き合いください。
- 政策金利の仕組みが簡単にわかる
- チェックしたい世界の4大中銀
- FXはなぜ金利の影響を受けるのか
- 利下げ・利上げがFXに与える影響
- 政策金利と取り入れたFXトレード戦略
政策金利について一番わかりやすく解説


FXでは「政策金利が重要だ」とよく言われています。そもそも政策金利って何なのでしょうか。
国が決める金利ってこと?
実は金利ってのがよくわからない・・・
任せて下さい!
まずは金利について最初の1歩から、
順番に教えていきます。
最初に、FXはひとまず置いといて、「金利とは何なのか」「政策金利とは何なのか」をわかりやすく解説していきます。
そもそも金利って一体何なの?
金利とは、預金をしたりお金を借りたりした時の利息の比率のことをいいます。
金利がつくものに以下のようなものがあり、それぞれ0.10%や0.05%などの利息の比率が決められています。
- 普通預金の金利
- 定期預金の金利
- クレジットカードの金利
- カードローンの金利
- 住宅ローンの金利
例えば、普通預金の金利が0.1%(毎月)だとすれば、100万円の預金に対して毎月1,000円の利息がもらえます。
一方、カードローンのようにお金を借りている場合は、返済金に利息が追加される仕組みです。100万円の借入で金利(毎月)が0.1%だとすれば返済金にプラス1,000円の利息を追加して支払う必要があります。
政策金利とは?
そして、政策金利とは上記で見てきたさまざまな金利のベースとなる標準金利のことです。よほど悪質な消費者金融でない限り、むやみやたらに、好き放題金利が設定できるわけではないのです。
ある程度の「金利の目安」が国の金融政策として提示されています。それが、政策金利です。
政策金利は、その時々の経済状況に合わせて変動しています。金利を上げたり下げたりすることを「利上げ」「利下げ」「据え置き」という言葉で表現しています。
- 金利を上げる → 「利上げ」
- 金利を下げる → 「利下げ」
- 金利を変えない → 「据え置き」
※FXでいう「金利」とは通常は「政策金利」のことを意味しています。
政策金利は誰が決めるのか
政策金利を決定するのは、国の中央銀行(セントラルバンク)です。
中央銀行とは、国の資産(預金・税金等)を管理する銀行で、三菱UFJや楽天銀行など民間の銀行とは異なります。一般市民が中央銀行を利用することはありません。
政府機関、地方自治体、金融機関が中央銀行を利用しています。
中央銀行の主な業務は大きく3つあります。


- 金融機関の預金や借入
- 国の資金の管理、経済・物価の安定化
- 通貨の製造と発行
これらの業務のうちで、FXと深く関わるのが「経済・物価の安定 = 政策金利」です。
中央銀行は、つねに「利上げ」や「利下げ」をして、「経済・物価の安定」を図っているのですが、この金利が通貨にも影響を与えることになります。
FXと金利の関係を理解する前に、なぜ「利上げ」や「利下げ」が物価や経済と関係するのかを見ていきましょう。
金利とインフレーションの関係
経済が成長すると物価が高くなるのは自然なことで、世界共通で2.0%の物価上昇が望ましいとされています。
2.0%以上に物価が上昇することをインフレ(インフレーション)といい、物価が下降することをデフレ(デフレーション)といって、どちらも経済的なダメージがあるといわれています。
そこで、中央銀行は過度なインフレ・デフレを改善するために金利を調整しているのです。
インフレが進むと・・・
インフレが進むと、消費を抑えるために「利上げ」が実施されます。クレジットカードや借入の利息が高くなるため、消費が少なくなって物価が下がる効果があるのです。
デフレが進むと・・・
デフレが進んだ時は、逆に消費を促すために「利下げ」が行われます。クレジットカードや借入の利息が低ければ、お金を借りたり買い物したりするのが容易です。消費が活発となり、物価を上げることができます。
金利と経済の関係
「利上げ」や「利下げ」は経済の動きとも密接につながっています。


「利上げ」を行うと・・・
物価を下げるために金利を高くすることで、企業や個人の借入や投資が減少し、景気が落ち着くことを意味しています。物価は下がるのですが、経済が低迷するリスクがあります。
「利下げ」を行うと・・・
一方、物価を上げるために金利を低くすることで、積極的な企業や個人の借入・投資が進みます。物価が上昇し、物価の上昇から再びインフレのリスクが生じることもあるのです。
政策金利は、物価や経済の安定を計るために、つねに上げたり・下げたりと調整されているのです。
4大中央銀行と政策金利
ではここで、影響力が大きい世界の4大中央銀行(米国、EU、英国、日本)を、この機会にご紹介しておきましょう。
FED(米国:フェデラル・リザーブ)
まず抑えておきたいのが米国です。
米国には中央銀行がありません。フェデラル・リザーブと呼ばれる機関が米国の中央銀行としての役割を果たしています。フェデラル・リザーブとは、国の金庫(資金・預金)を意味する言葉で、FED(フェド)やFRB(エフ・アール・ビー)とも呼ばれています。
世界経済に最も大きな影響力を与えるのが、米フェデラル・リザーブが発表する政策金利です。米国の政策金利を決める議会のことをFOMC(エフ・オー・エムシー)といい、FOMC政策金利の発表に世界中が注目しています。
パウエル議長が金利を決める様子(イメージ)


ここ数年のFEDのトップはジェローム・パウエル議長で、米国の金利を発表する役割を担っています。わずか0.25%の違いでも、米国経済や米ドルには大きな影響を与えるため、パウエル議長のプレッシャーは言葉で表せないほど高いといえるでしょう。近年では利上げの発表を行うごとに、体重を落としているようでした。
パウエル議長は、あるインタビューにて、「トランプ大統領の時にはよく電話がかかってきていた」と、大統領からの圧力があることを辛そうに語っています。「ストレス解消法は?」との問いには、「バイクで走りに出かける」とアメリカンな回答でした。
参照:Fed Chair Powell Speaks to David Rubenstein – Youtube
- 5.50%(11回利上げの後、据え置きにある状況)
ECB(EU:ヨーロピアン・セントラル・バンク)
米国の次に注目度が高いのがEUの政策金利です。EUは、フランス、ドイツ、イタリア、ギリシャ、デンマーク、ポーランドなど欧州の27か国が加盟する連合体で、ECB(イー・シー・ビー)がEUの中銀としての役割を果たしています。
紀元前、古代から貿易や建造物の数々で、独特のブランド性を築き上げていることがEU諸国の強み。小国ながらも、経済大国として名を連ねる国も少なくありません。EUの政策金利も、米国同様に経済や通貨に深い影響を与えています。
インフレと経済成長のバランスを図るEU総裁(イメージ)


かつては、EUも日本同様に低金利を維持し続けていましたが、インフレ・エネルギー高騰に立ち向かうために、泣く泣く利上げを余儀なくされました。
EUに加盟する国々は経済格差が大きいことが特徴です。経済に致命的なダメージを与えずに、インフレを抑えるためには、絶妙な金利操作が必要だといわれています。ECBのトップ、ラガルド総裁は、自転車で綱渡りをするに等しい状況をこなしていると評判です。記者会見の時には、たまに質問を聞いてないふりをしたりと経験豊富なテクニックを見せています。
参照:ECB綱渡り的な利上げに向け大詰め段階 – Bloomberg
- 4.50%(10回連続利上げの後、据え置き状態)
BOE(英国:バンク・オブ・イングランド)
続けて抑えておきたい中央銀行は英国です。英国の中央銀行は歴史あるバンク・オブ・イングランド、BOE(ビー・オー・イー)とも呼ばれています。BOEの設立は、何と1694年!で320年以上の実績を持ちます。
世界最古の中央銀行は、スウェーデンのリクスバンクの1668年。BOEは2番目に古く、現在の中央銀行の基盤となるシステムを確立した銀行です。


BOEのトップはベイリー総裁。2021年11月に、世界的な「利上げピーク」の先駆けとして0.50%の「利上げ」を突然発表し世界を驚かせました。2022年以降、英国のインフレはピーク時で10%を超え、賃上げのストライキが相次いで起こりました。
空高く舞い上がるインフレの風船を追いかけるかのごとく、英国は14回連続で利上げを行っています。国民の非難を浴びて、2024年2月にはベイリー総裁が早期での利下げの考えを述べました。サプライズの利下げ発表がいつになるか注目です。
- 5.25%(14回連続利上げの後、据え置きが続く)
BOJ(日本:日本銀行)
さて、世界でも極めて異例の政策金利で、七不思議の1つになろうとしているのが日本の中央銀行である日本銀行です。日本銀行はバンク・オブ・ジャパンを略してBOJ(ビー・オー・ジェイ)と表記します。日本では、「にちぎん(日銀)」の愛称で親しまれて(?)います。
なぜ日銀が異例なのかというと、まず日本の政策金利は1999年あたりにゼロ%前後に低下してからほとんど変わっていないということ。コロナが猛威を振るおうと物価が上昇しようと日銀の政策金利は不動です。
とくに近年、世界中が利上げに走る中、低金利(マイナス金利)を維持し続ける日銀にしびれを切らしている日本国民も少なくないようです。ある意味、ここまで低金利に執着する日銀は驚異的だとも言えます。
金利を操作する日本銀行の植田総裁(イメージ)


現在の日銀のトップは、植田総裁。植田総裁は、黒田前総裁の「異次元緩和・黒田バズーカ」を引き継いだあと、年功序列のしきたりに従いつつも、ようやく「マイナス金利」から脱却しました。しかし、変わらず石橋をたたいて渡る慎重さを見せています。日銀は過去の円高時に大量のドルを仕入れていて、売り時を吟味しているとの噂もあるようです。


ちなみに黒田前総裁の「黒田バズーカ」とは、大量に国債を購入して金利を下げるテクニック(国債を買うと金利が下がる)のことをいいます。溜まりにたまった国債を売り、金利を上げて(国債を売ると金利が上がる)いくことが、植田総裁に期待されています。
参照:植田日銀に政策金利は引き上げられない – 週刊エコノミスト
- 0.10%(G7国で唯一、低金利を維持)
簡単に見てきたように、政策金利には、
中銀それぞれのドラマがあって
楽しめるかもです。
※なお、各国の政策金利はセントラル短資FXのサイトにて、グラフでご覧になれます。
※また、政策金利に関する情報を調べたい時は、Xではわかりやすいコメント・解説が多くおすすめです。




FXはなぜ金利の影響を受けるのか?


では、いよいよ本題です。利上げや利下げから通貨の価格が変動するのはなぜでしょうか。FXと金利の仕組みを図解やチャートでわかりやすく見ていきます。
FXと金利の関係は思った以上に
シンプルです。


利上げがFXに与える影響
なぜ、金利が高い方に資金が流入するかというと、定期預金と同じ仕組みです。
定期預金をしようと思った時には、少しでも金利が高いプランを選ぶ人が多くなります。それと同じように、「5.0%の金利がつく米ドル」と「0.1%の金利がつく円」で比較するなら、当然ながら5.0%の金利がつく米ドルに資金が集まります。


金利が高い通貨に資金が流入しやすい仕組みから、「利上げ」は価格高騰のきっかけとなりやすいのです。
どれくらい価格が動くのか
チャートで例を見てみましょう。
BOE(英中銀)が4.25%の利上げに踏み切った時(2023年3月)
2023年3月、BOEは0.25%の利上げを実施「4.25%」の政策金利を発表しました。11回連続利上げとなり、GBPJPYはこれまでにないペースで上昇。158.00から174.20の高値まで昇りつめています。
GBPJPY(日足チャート:早送り)


利上げ発表当日は、1日で約180pips。2か月で1,600pipsの上昇となりました。
EUが0.75%の利上げを発表した時(2022年9月)
EUは2022年7月より利上げを開始。8月の政策金利は「0.50%」、9月には「0.75%」の利上げを発表しました。長年にわたる0%金利のブレイクにてEURは対円で勢いよく上昇します。
EURJPY(日足チャート:早送り)


一週間で500pips、2か月後には約1,200pipsも上昇と従来では考えられないペースです。
利下げがFXに与える影響
金利が高い方に資金が流れるということは、「利下げ」は売りのサインとなるわけですが、さらに投資家心理が悪化して売りが加速することがあります。
通常、好景気でインフレーションが進んだ時の改善策として「利上げ」が行われていて、「利下げ」とはまったく逆のパターンになります。つまり、「利下げ」とは経済が低迷していて物価が下がっている、あるいは、経済の低迷が予想されていることの表れです。


新型コロナウイルスの感染拡大時には、経済の悪化が予想されて「利下げ」「通貨安」が進みました。このようなイメージから、「何か、隠れた不安要素があるのではないか?」と深読みした売りが入りやすくなるのです。
米国が緊急利下げを発表した時(2020年3月)
2020年、新型コロナウイルスの感染拡大が悪化した時には、利下げピークが起きました。3月3日に、FOMCが緊急利下げを発表すると米ドル売りに火をつけました。
USDJPY(4H足チャート:早送り)


USDJPYは、107.90(こんな時代もあった!)から3日間で100.90まで急落。700pipsの大変動です。
しかし、この後ですぐにFOMCが巨額の緊急支援策を発表し、ドルは上昇に向かいます。
スイス中銀が予想外の利下げを発表した時(2024年3月)
SNB(スイスの中央銀行)は、2024年3月にインフレが落ち着いたため予想外の「利下げ」を発表しました。発表後に、スイスフランはほとんどの通貨に対して下げに向かいます。低金利の日本円ですら、買われる状況となりました。
CHFJPY(4H足チャート:早送り)


170.60の高値から、166.48の安値まで急落。1週間で約400pips下がりました。
金利差がFXに与える影響
金利差が拡大するほど、低金利通貨から、高金利通貨へと資金が流れやすくなります。
ただし、経済が不安定な国の通貨(マイナー通貨・新興国通貨)は、メジャー通貨よりもリスクが高いため、資金の流入は限られています。
主要国の政策金利の推移


上図チャートを見るとわかるように、政策金利がほぼ横ばいで変わっていないのは日本だけです。他国が「利上げ」を行う状況では、日本円から資金が流出しやすくなるわけです。
もともと高金利の通貨よりも、米ドル、ユーロ、英ポンドのように、低金利だったものが高金利に向かうことで注目度が高くなるのです。
2022年以降は日本以外が一斉に利上げを行ったため、日本円の価値はその他主要国通貨に対して下がり続けているのです。
通貨インデックス比較チャート(4H足チャート)


※通貨インデックスとは、通貨の価値を総合的に算出した指数のことで、単独での価値を表したものです。
Tradingiviewの通貨インデックス一覧:https://jp.tradingview.com/markets/indices/quotes-currency/
他国と日本の金利差から円安が止まらない(2024年1月~)
2023年12月は、BOEの利下げ予想とBOJの利上げ予想がGBPJPYを下降に向かわせたものの、勝負に出れないBOJ。結局のところ日銀会合が近づくたびに、GBPがせっかく下がりかけても日本の政策金利は変わらないという結果でした。またしても円売りを再燃させ、GBPは200円に近づこうとしています。
GBPUSD(日足チャート)


2024年1月のGBPJPYは178.662、1か月後に約1,000pips上昇。4か月後には2,000pipsとさらなる円安を更新しています。
USDJPY(15分足チャート)


当然のごとく、対米ドルでも円は売られ、とうとう34年ぶりの円安158円台に突入しました。
金利差が縮まらないかぎり、円安を食い止めることはできないようです。
以上見てきたように、金利はFXでは
最も重要なファクターとなり得るのです。
政策金利を取り入れたFXトレード戦略


政策金利がFXに与える影響は絶大です。通貨の価値は金利がすべてだといっても過言ではありません。FXでは、政策金利をチェックしながらトレードすることは必須だと言えます。
どのように政策金利で
トレードをすべきか・・・
ここでは、政策金利を取り入れたFXトレードのやり方を解説していきます。
政策金利でFXトレードするポイント
政策金利をチェックしながらトレードする流れやポイントを見ておきましょう。
- 政策金利発表スケジュールを抑えておく
- 市場予想・市場観測をリサーチ
- 複数のシナリオに沿ってトレード
①最低でもチェックしておきたい政策金利
- 米国:FOMC政策金利(米中銀会合)
- EU:ECB政策金利(欧州中銀会合)
- 英国;BOE政策金利(英中銀会合)
- 日本:BOJ政策金利(日銀会合)
スケジュールは、FX業者の経済指標カレンダーから確認できます。日時を調べておきましょう。
②市場予想のリサーチは必須!
次に、重要なのが市場予想や市場観測をリサーチしておくことです。プロや他のFXトレーダーは、発表予定の政策金利についてどのように予想しているのか、どのように考えているのかを知ることで、戦略の材料になります。
市場予想のおすすめサイト
- 経済予測・経済見通し – ニッセイ基礎研究所
- 金融政策 – 日経新聞
- Global Ecnomy & Policy Insight – NRI
- ビジネス短信- JETRO
- 政策金利検索 – X (初心者おすすめ!)
例えば・・・
「経済・ 物価の見通しが実現し、基調的な物価上昇率が上昇していくとすれば、金融緩和度合いを調整していくことになるが、当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている」とした。
by sputnik_jp – X
といった情報を読むことで、「物価上昇率」が利上げの決め手なのかな?と探ることができます。
「米銀大手シティ、FED利下げ予想を年内125bpsから『100bps』へと修正。開始時期は7月。」
by Yuto_Headline – X
また、別の情報では、大手シティ銀行は、100bps(1.0%)の利下げを7月に予想しているのか・・・と材料が1つ得られました。
政策金利でトレードする際には
市場がどう見ているのか、
情報収集が決め手となります!
③シナリオに沿ってトレード
情報収集がある程度完了したら、最低でも2パターンぐらいのシナリオを想定しておきましょう。
シナリオの例
- 市場予想どおりにBOJの利上げがあれば、円が買われるだろう
- ただ、もし米国の経済データが強ければ米国の利下げの可能性がなくなりドルが買われる
- 米国の利下げの可能性が強まり、BOJの利上げの可能性が強まればドルは急落する
など・・・複数の根拠・パターンを想定してトレードの準備していきます。
トレード戦略の例


FOMCは金利据え置きでパウエルの利下げ言及から、ドルが売られています。小売り売高は強くとも、PPIやCPIが下がっていたことで、日銀が利上げを匂わせるなら下降の可能性が強まるでしょう。
BOJ政策金利の予想は-0.1%、利上げの言及があるなら「買い」で、青の上昇トレンドラインの方向に向かうと見ます。反対に、BOJが利上げの可能性を否定するなら「売り」で、赤の下降トレンドラインに沿って下がると予想。
というように政策金利の発表を目安にトレード戦略を立てていけるのです。
- いくらでエントリーするか(成行 or 指値)
- ターゲットはいくらか(成行 or 指値)
- 損切はどこにするか(成行 or 逆指値)
トレード戦略のシミュレーションには
FX検証ソフトが役に立ちます。


毎日変動する金利をチェックしてみよう
政策金利の発表だけでなく、実際の金利はその時々の状況によってつねに変動しています。毎日変動する金利を目安にトレードする方法もあります。
10年国債の金利と通貨の価格は連動する傾向にあり、国債の金利動向からFXトレードのヒントを得ることができます。
日本10年国債利回りとFXの関係
日本10年債の金利


2023年後半あたりから、日銀の政策金利の修正説が強まってきました。従来は、国債の購入で10年債の金利を0.5%程度に抑える方針でしたが、10月以降には1.0%までの金利の上昇を容認したこと発表されました。日本10年債の金利は10年ぶりに0.755%を超え、GBPJPYは下降に向かいます。


- 10年債の金利が上昇 → 通貨の価格が上昇しやすい
- 10年債の金利が下降 → 通貨の価格が下がりやすい
なぜ、国債の金利と通貨の動きは連動しやすいのか


債券とは借用書のようなもので、最初から満期日になると返還される金額が決められています。例えば100万円の債券を途中で売ると99万円、でも返還日には100万円でかえってくるため99万円にプラス1万円の金利がつく計算になります。


債券を売る人が増えて価格が下がるほど、金利が高くなる仕組みになっているのです。
- 債券を売る → 債券の価格が下落 → 金利が上がる
- 債券を買う → 債券の価格が上昇 → 金利が下がる
そして、債券の金利が上がるということは、債券が売られている状態です。国債は国の財源ですから、国債の量が減るということは通貨の量が減っていることになり、通貨の価値が上がっていくのです。
- 国債を売る(金利が上がる)→ 通貨量が減少 → 通貨の価格が上昇
- 国債を買う(金利が下がる)→ 通貨量が増加 → 通貨の価格が下落
ですから、国債の金利と通貨の価格が連動する傾向にあるのです。
主要国の10年債のチャートはTradingviewでリアルタイムで見ることができます。
債券は、正直ややこしいので、
金利と通貨は連動しやすい、ってことだけ
覚えておけばよいのです。
金利と反対の動きをする商品
そして、金利と全く逆の動きするのが株式や金、暗号資産などです。
金利が上がると・・・
- 株式 → 高金利によって企業の経済活動が縮小 → 株安になりやすい
- 金 → 金は金利がつかないため、通貨が買われると下がる傾向にある
- 暗号資産 → 金利がつかないことや、企業の経済活動の縮小で売られやすい
金利が下がると・・・
- 株式 → 低金利で企業の経済活動が向上 → 株高に向かいやすい
- 金 → 金利による通貨の魅力が減少し金が買われる、通貨に不安がある時も買われる
- 暗号資産 → 金利や通貨に魅力がなくなり資金が暗号資産に向かいやすい
金や株式の動きがヒントに
なったりもするのです。
政策金利でトレードする際のコツ・注意点
最後に、政策金利トレードで成功するコツと注意点を簡単にまとめておきました。
情報収集は断片的にわかるものだけを拾う!
ファンダメンタルズのコツは、すべての情報をわかろうとしないことです。経済関連の記事は、専門用語だらけでぱっと見で拒否反応を起こすことも多々あります。
しかし、慣れてくれば用語の意味もいつの間にか理解できるようになりますので、最初は断片的にわかるものだけを拾っていくのが成功のコツです。
「おっ!GDPが上がると金利が上がる可能性があるのか!」
「雇用統計なら、なんとなく意味がわかるぞ・・・」
など、部分的にわかる内容は結構多いものです。
発表そのものよりも思惑から動くことも多い!
金利の発表そのものよりも、事前の利上げへの期待から相場が盛り上がってしまうケースもあります。


「噂で買って事実で売る」というケースです。つまり予想通りの発表があった途端に熱が冷めて、一斉に売られるといった状況もあるので注意しましょう。
サプライズの発表では、大きな値動きが狙える!
政策金利トレードで最も重要なのが「市場予想」です。状況にもよるのですが、概ねの値動きの目安は以下のとおり。
- 市場予想を下回る → 急下降の可能性
- 市場の予想通り → 短時間の値動きで終わりやすい(価格が戻る)
- 市場予想を上回る → 価格の高騰・急騰につながる
金利が高ければ必ず上昇するというわけではない!
ただ、必ずしも金利が高ければ通貨の価値が上がる、というわけではないことが金利の落とし穴です。




例えば、トルコリラの政策金利は50%程度にまで上昇していて高スワップが狙えます。しかし、一方では対ドルや対円では安値を更新し続けています。米ドルやユーロ、英ポンドに関しても同様のことが言えますので、金利のみに依存しすぎても危険だということです。


ちなみに、政策金利と合わせてチェックしておきたい経済指標を下記でご紹介しています。合わせて参考にして下さい。
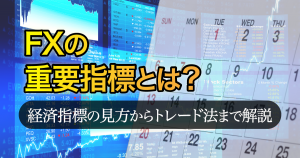
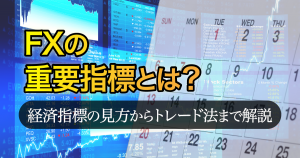
まとめ
FXでは、大きくテクニカル分析とファンダメンタル分析と2つの分析手法に分けることができます。テクニカルだけでは、複雑な市場心理が読み取れないことが多く、ファンダメンタルだけでは適切な売買ポイントが計りづらいのが実状です。
テクニカルとファンダメンタルズと双方をバランスよく取り入れることで、勝てるトレードへとつながります。
ファンダメンタルズに興味がなかったテクニカル派も、金利とFXの関係を意識することでトレードスキルは一気に向上します。難しく思えがちな金利の話も、フタを開けてみると意外と簡単な理論でした。ぜひ、今回の記事を参考に、両刀を使いこなす最強のFXトレーダーへとのし上がって行きましょう。




コメント コメント 0